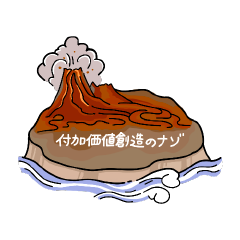現在YouTubeにて、リーゼント・マネージャー岡田兵吾さんとの対談セッションを連載しております。今回は、第二のナゾ、すなわち付加価値創造のナゾ、及び第三のナゾ(グローバル化のナゾ)につきまして、見逃してはならない重要なポイントをおさらいしておきたいと思います。
まず、岡田兵吾さんは日本はハイコンテキスト、すなわち、いわゆる「阿吽の呼吸」や暗黙の信頼ベースでコミュニケーションが成り立つ社会であるとおっしゃっておりました。ハイコンテキストというのは、言葉以外の前提となっている背景や文脈、あるいは非言語的な、たとえば表情ですとか声のトーンですとか、こういったものを前提としてコミュニケーションが成り立っているような文化や状態のことです。いちいち細かいことまで言わなくてもわかるでしょといった「阿吽の呼吸」で会話が成り立つというのは日本文化の特徴と言って良いと思います。逆に言いますと、多民族・多言語で構成されているような海外の地域・社会ではローコンテキスト、つまり前提事項を明確に示さないと会話が成り立たないような、そういうコミュニケーションが必要とされているということになる訳です。
この点は、海外との比較、あるいはグローバルにビジネスを拡大するという意味におきまして、決して見逃してはならない大変重要な観点です。日本にいると当たり前のことでも、異なる考え方や文化に接する際には、順を追って論理的に説明する必要があるということです。だからこそ、昨今のグローバル化したビジネスにおいては、データ重視あるいは「データ・ドリブン」のアプローチが推奨され、客観的・体系的で科学的な考え方や物の見方が必要とされているということです。
これをビジネスで付加価値を創造するという側面から見て参りますと、これまでの日本においては、事細かにやり方を決めなくても、「上手に売ってください」とか「あいつに任せておけば何とかなる」といった具合、つまり「ハイコンテキスト」なやり方でビジネス、特に営業プロセスが成り立っていたということができるかと思います。
もちろん、従来からのモノの売り方で十分に売り上げが伸びている、お客さんとも阿吽の呼吸で会話が成り立っているよという企業さんにおいてはこの点はそれほど重要ではないのかもしれません。しかし、長期的に見ても本当に大丈夫でしょうか?新たな法規制や新たな新規参入にも耐えられるということでしょうか?あるいは次世代を担う若手社員が順調に成長しているということでしょうか?
リーゼントマネージャー岡田兵吾さんがおっしゃる海外との比較は大いに参考になるお話だったと思います。
海外との比較が何故これほどまでに重要かと言いますと、日本国内で起きている変化が、たとえわずかなものであったとしても、比較対象がないと気が付きにくくなるからです。短期的には僅かであっても長期的には大きな変化となり、気づいた時にはもう手遅れといった事態が危惧されます。わかりやすい昨今の例としましては地球温暖化や人口減少などでしょうか。これらは非常にクリティカルな課題であるものの、短期的には「何とかなるだろう」や「今すぐの課題ではない」といった捉え方になりがちだということです。
教育の問題についても触れておりました。大学を卒業する22歳で教育は終わりではなく、世界では生涯学習に変わってきている。しかし、日本ではこれがないから変化に気づかないとも指摘しておられました。気づかないままですと、変化が必要だということにも気づかないままとなります。ビジネスにおける経営方針や業務内容もそれまでのやり方から何ら変わらない結果になるということです。例えば「良いモノをたくさん作れば売れる=儲かる」というのは、我々が50年くらい前に経験した高度経済成長期における成功体験と言って良いと思いますが、多くの企業の皆様がこれをいまだに引きずっているように見えます。昨今の経済停滞を見ても明らかなように、今や価値訴求のしかたを変えていく必要がある訳ですが、何をどのタイミングでどのように変えていく必要があるのかを考えていく必要があるということです。
日本はモノづくり大国と言われますが、内需に大きく依存しているという指摘もございました。人口減少の中、外需シフトが必要となる訳ですが、その力が弱く、次の打ち手を模索することに消極的である点を問題視しておられました。そういったことの根本的な原因は、新卒一括採用や年功序列にあるのではということにつながります。いわゆる「下請け叩き」といった現象、これは私が指摘したことですが、創造すべき価値を増大させるのではなく縮小させてしまう結果となる気がしてなりません。
それから、日本は投資しておらず、人件費を抑えてきたことで経済発展が阻害されている点も見逃せません。勤勉に働くのは日本人、日本企業の良さだと思いますが、それだけでは価値を生まない。そういう時代になってきているということです。世の中が多極化する中、ここで競争しようとしていない現状を指摘しておられたかと思います。
こういったご指摘は、私が掲げる第三のナゾ(グローバル化のナゾ)につながって参ります。
海外で仕事をされていて、外から日本を見ると、そもそも、日本はグローバルの良さ(各国の良さ)を見てないし、知らない、慣れていない。それゆえチャンスを逃しているのではないか、というご指摘です。岡田さんご自身の生い立ちがいわば閉鎖的な環境だったので、外に出てみたいという好奇心が自ずと生まれていたとおっしゃっておられましたが、彼が指摘した疑問点は、なぜ日本企業やそこで働く人たちはそのように好奇心を持って外に出ていかないのか?ということでした。組織間の横のつながりを推進するような日本企業が少ないのではというご指摘もございました。日本に限らず世界中の多くの企業が必要な人材を確保するのに苦労しており、さまざまに工夫している中、グローバル社会の中で日本企業が必要とされる組織や風土づくりのキーワードとして、Best Place to Work、心理的安全性、assertivenessといった言葉で説明されていたかと思います。
ここで用語の補足をいたします。
「Best Place to Work」 というのはあまり難しい言葉ではないと思いますが、要は「最高の働きがいのある会社」という意味です。
「心理的安全性」とは、組織内で自分の意見や感情を安心して表現できる状態であり、対人関係におけるリスクある行動(質問する、間違いを指摘するなど)をとっても、拒絶されたり罰せられたりしないというチームメンバー間の共有認識のことです。
「アサーティブネス(assertiveness)」とは、自分も相手も尊重しながら、自分の意見や要求を率直に、かつ適切に表現するコミュニケーションスキルや態度のことです。単に自己主張するだけでなく、相手の意見や感情も理解し、対等な立場で建設的なコミュニケーションを図ることを目指すものです。
これらによって、新たなアイデアや付加価値が生み出されていく、そのような時代だというご指摘だったと理解しております。まだまだ女性に不利な労働環境が残っていたり、上司とのコミュニケーションが難しいなど、日本にはこういった観点からの改善の余地が多く残されているように思います。権限委譲の必要性についてどう考えるかを尋ねてみたところ、リーダーというのは何も役員といった組織上上にいる立場の人たちだけのものでなく、SME(Subject Matter Expert)と言われるような各専門分野のリーダーを従業員各人が自覚を持って務められるような体制が必要ではないかということだと理解します。これを推進しないままですと、従業員自らが考え、行動するといった競争力のある企業になっていかないということだったかと思います。
リーゼント・マネージャー、岡田兵吾さんとの対談はいよいよ最終回となります。ぜひご期待ください。